相続で覚えて
おくべき基礎知識
- TOP
- 相続で覚えておくべき基礎知識
basic-knowledge急な相続で慌てないために基礎知識を紹介
いえむすびは、江戸川区、市川市、船橋市の不動産会社です。地域のお客様の不動産や相続に関するお悩みに、これまで数多く応えてきました。相続は突然発生し、関連する手続きも非常に複雑です。当事者になった方は、混乱してしまうこともあるでしょう。ここでは、当社が相続で覚えておくべき基礎知識を紹介します。急な相続で慌てないためにも、事前に知識を身につけておきましょう。
不動産相続をする人が知っておくべきこととは
相続登記は、相続が発生したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。相続に関わる親族間のトラブルを避けるためにも、早めの申請が重要です。
不動産相続手続きの流れ
相続人の確定

相続が発生したら遺言書の有無を確認しましょう。相続人を確定させることが、最初のステップです。遺言書は、自宅以外にも法務局や公証役場に保管されているケースもあります。遺言書がない、もしくは遺言書の内容に相続人が異議を唱えている場合は、遺産分割協議を行いましょう。協議がまとまったら、相続財産の記載と相続人全員の署名・押印がある「遺産分割協議書」を作成し、相続人を確定させます。
相続登記の必要書類を準備
相続する不動産を特定するために、必要書類を用意します。なお、代理人が申請する場合には委任状が必要です。
| 書類 | 入手方法 |
|---|---|
| 登記済権利証/登記識別情報 | 自宅や貸金庫などを探す。 |
| 固定資産税納税通知書 | 市区町村から毎年4~5月に届く。 |
| 登記事項証明書 | 管轄の法務局に請求。 |
| 名寄帳 | 市区町村役場の資産税課に請求。 |
相続登記に必要な書類は以下の通りです。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 必要な書類 | 遺産分割協議の場合 | 法定相続分による場合 | 遺言による場合 | 取得場所 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言書/遺言書情報証明書 | ◯ | 自宅、法務局、公証役場 | ||
| 遺産分割協議書 | ◯ | 関係者間で作成 | ||
| 亡くなった方の戸籍・除籍謄本 (出生から死亡まで)及び戸籍事項証明書 |
◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 | |
| 亡くなった方の戸籍謄本 (死亡に関する事項を含む) |
◯ | 本籍地の市区町村役場 | ||
| 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 | ◯ | ◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 (戸籍事項証明書) |
◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 | |
| 取得する人の戸籍謄本 (戸籍事項証明書) |
◯ | 本籍地の市区町村役場 | ||
| 相続人全員の印鑑証明書 | ◯ | 住所地の市区町村役場 | ||
| 相続人全員の住民票 | ◯ | 住所地の市区町村役場 | ||
| 取得する人の住民票 | ◯ | ◯ | 住所地の市区町村役場 | |
| 相続関係説明図 | ◯ | ◯ | 作成者(弁護士や司法書士など) | |
| 固定資産評価証明書 | ◯ | ◯ | ◯ | 不動産所在地の 市区町村役場 |
Pickup相続登記の義務化について

2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。不動産の所有権を相続した場合は、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に、不動産の名義を変更しなければなりません。「戸籍謄本等の必要書類の収集に時間がかかる」「相続人が病気で対応できない」などの正当な理由がないにもかかわらず相続登記を怠ると、10万円以下の過料が課せられます。
相続登記の手順については法務局ホームページをご覧ください。
不動産相続にかかる諸費用を知ろう
不動産を相続すると、さまざまな費用が発生します。税金や書類取得費用、司法書士や税理士への依頼料などを、以下で確認していきましょう。
相続税

相続税は、相続財産の時価総額から、基礎控除の金額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引いた額に課税されます。土地を相続した場合は、時価総額を確認するために国税庁ホームページの路線価図・評価倍率表を確認しましょう。建物を相続した方は、固定資産課税明細書、または固定資産評価証明書の固定資産税評価額欄を確認してください。
不動産相続に関する相続税の特例や、控除などは、以下より当てはまるケースを探しましょう。それぞれ適用条件は異なるので、ご自身の不動産が当てはまるかどうか分からない際は、不動産会社への相談をおすすめします。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 概要 | |
|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 相続した土地の最大330平方メートルまで、不動産評価額が最大80%減額される。 |
| 配偶者の税額の軽減 | 遺産額が「1億6,000万円」「法定相続分」、いずれか多いほうの金額まで非課税になる。 |
| 配偶者居住権 | 亡くなった方が所有していた建物に、配偶者が住み続けられる権利。相続税は非課税になる。 |
| 相続財産と譲渡した場合の取得費加算の特例 | 相続が開始された日の翌日から3年10ヶ月以内に相続財産を売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算できる。これにより、譲渡所得税の負担を減らせる。 |
| 相続した空き家を売却した場合の特例 | 相続後に空き家になった家を売却した場合、譲渡所得金額から最高3,000万円が控除される。 |
固定資産税・都市計画税
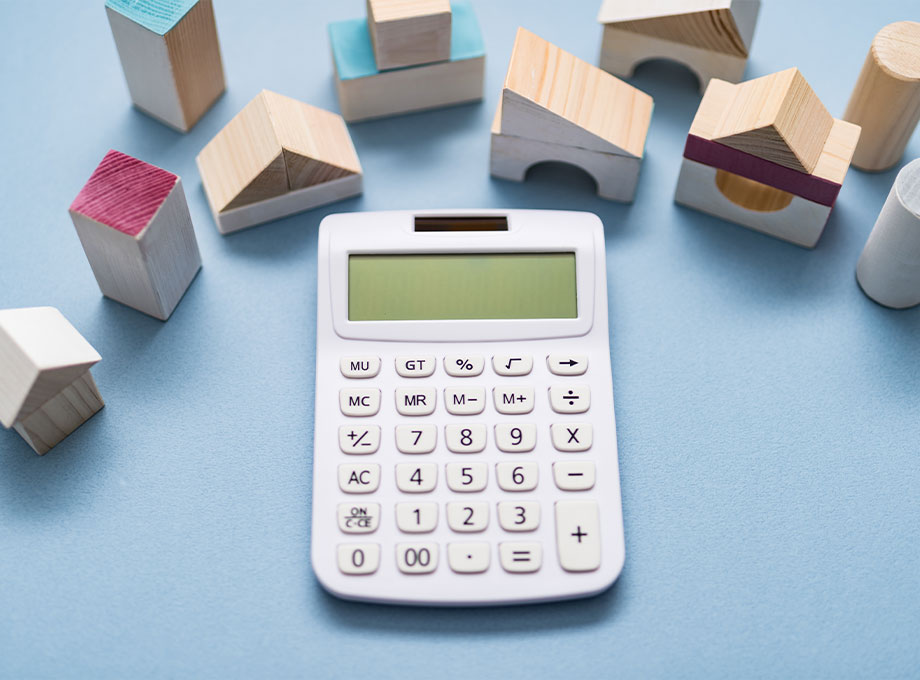
毎年1月1日時点で所有している不動産に自治体から課される税金が、固定資産税・都市計画税です。毎年4~6月に、納税通知書と払込票が送られてくるので、記載されている内容を確認しましょう。
譲渡所得税

相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税・住民税・復興所得税が発生します。税率は不動産の所有期間に応じて短期・長期に分けられ、以下のように変わります。短期・長期の判定には、亡くなった方が所有していた期間も含まれるため注意しましょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所有期間 | 所得税(復興所得税) | 住民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以内 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
登録免許税
相続を原因として不動産の所有権移転登記申請を行う際、固定資産税評価額の0.4%分の収入印紙を貼付して登録免許税を納める必要があります。
必要書類の入手先と取得費用
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 入手先 | 書類 | 取得費用(非課税) |
|---|---|---|
| 本籍地の市区町村役場 | 戸籍謄本 | 450円 |
| 戸籍の附票 | 450円(地域によって異なる) | |
| 除籍謄本 | 750円 | |
| 法務局 | 登記事項証明書 | 600円(不動産1件) |
| 住所地の市区町村役場 | 住民票 | 200円 |
| 住民票の除票 | 300円 | |
| 印鑑登録証明書 | 200円 | |
| 不動産所在地の都(市) 税事務所や市区町村役場 |
固定資産評価証明書 | 土地5筆まで200円 家屋5棟まで200円 |
※地域によって費用は異なります。
司法書士・税理士への依頼料
相続や登記には煩雑な手続きがあります。そのため、司法書士または税理士に依頼するのが一般的です。報酬は、司法書士の場合3~10万円、税理士の場合相続財産の0.5%~1%が相場となります。
不動産を相続するときに注意しておくべきポイントとは
相続人が複数いる
トラブルを避けるため、不動産登記を共有名義で行うのは避けましょう。遺産分割協議では、以下のような分割方法がおすすめです。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 分割方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 複数の不動産がある場合、不動産ごとに相続人を決める。 | 不公平になることも。 |
| 更地にして分筆登記する。 | 分け方次第で売却や建て替えが困難になるケースも。 | |
| 代償分割 | 相続人の一人が単独所有者になるために、ほかの相続人に代償金を払い、共有の持ち分を買い取ることになる。 | 事業の承継や、すでに居住している場合に選択されることが多い。代償金が高額になることが多く、現実的ではないとされる。 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、得た現金を分配する。 | もっとも合理的で公平。 |
不動産を相続したくない場合は
「老朽化した家を相続したくない」「住むつもりがない」といった相続したくない事情がある場合は、以下の方法も検討しましょう。
| 相続放棄 | 不動産売却 | 限定承認 |
|---|---|---|
| マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も一切引き継がないこと。 | 相続した不動産を売却し、資金に変える。 | プラスの範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐこと。 |
| 相続放棄 | マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も一切引き継がないこと。 |
|---|---|
| 不動産売却 | 相続した不動産を売却し、資金に変える。 |
| 限定承認 | プラスの範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐこと。 |
| 寄付 | 国庫帰属 |
|---|---|
| 社会福祉法人などに不動産を寄付すること。 | 相続土地国庫帰属制度を利用し、土地を国に返すこと。 |
| 寄付 | 社会福祉法人などに不動産を寄付すること。 |
|---|---|
| 国庫帰属 | 相続土地国庫帰属制度を利用し、土地を国に返すこと。 |
なお、相続放棄や限定承認の場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
空き家になっている場合

空き家は放置し続けると「管理不全空き家」として認定され、固定資産税などの納税額が最大6倍になるケースも。不要な支出を避けるためにも、なるべく早めに売却しましょう。なお、相続前に空き家だった理由が、老人ホームへの入居や入院であれば、「小規模宅地等の特例」「相続した空き家を売却した場合の特例」を適用できる場合もあります。
不動産を売却する場合

不動産を売却すると、売却益を相続税の支払いにあてられます。また、複数の相続人で財産を分割する場合にもトラブルが起きにくいのも特徴です。不動産売却の方法は、買主を見つける「仲介売却」と、不動産会社が買主となる「不動産買取」があります。一般的に仲介の方が売却価格は高くなりますが、平均3~6ヶ月程度かかることをあらかじめ想定しておきましょう。
相続税の支払い期限は相続発生から10ヶ月なので、仲介売却を検討している場合は、なるべく早く不動産会社に相談することが重要です。
相続する住宅が借地に建っている場合

借地に建っている家を相続する場合、借地権も相続することが可能です。相続の際に地主の承諾は不要で、土地の賃貸借契約書の名義を変更する必要もありません。ただし、相続後に建て替える場合や、借地権を売却する場合には、地主の許可が必要となります。また、借地権にも借地権割合に応じた相続税がかかることは把握しておきましょう。
被相続人が認知症になる前に対策しよう

被相続人が認知症になり、意思能力がないと判断された場合、認知症発症以後に作成した遺言書や契約は無効になるケースがあります。こうした事態を防ぐため、意思能力があるうちに公正証書遺言をはじめとする有効な遺言書を作成するか、任意後見制度の利用をおすすめします。意思能力がない場合は法定後見制度を利用するなど、事前にしっかり対策を講じることが重要です。
事前に不動産価値の確認を

不動産を複数人で相続する場合、「分割方法で意見が合わない」といったトラブルを防止したり、不動産を有効活用したりするためには、相続前に不動産の価値を確認しておくことが重要です。不動産の評価額には、「地価公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」の4種類があります。ただし、売却した場合の相場と相続税を算出する評価額は異なるため、注意しましょう。
相続の発生前に不動産を売却しても◎
不動産の相場価格が高い、小規模宅地等の特例が使えない、不動産が市場のニーズに合わない場合は、相続が発生する前に不動産の売却を検討することをおすすめします。
Pickup相続に強い不動産会社に
相談しよう

不動産会社によって、得意分野はさまざまです。相続に関する相談は、不動産相続の実績とノウハウがある不動産会社に行いましょう。税制優遇制度や、顧客ごとの相続対策に関する的確なアドバイスを受けられるはずです。
「いえむすび」は、不動産相続に関するさまざまなご相談に対応してきた、地域密着型の会社です。どんな小さな疑問でも親身に精一杯対応いたします。相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

